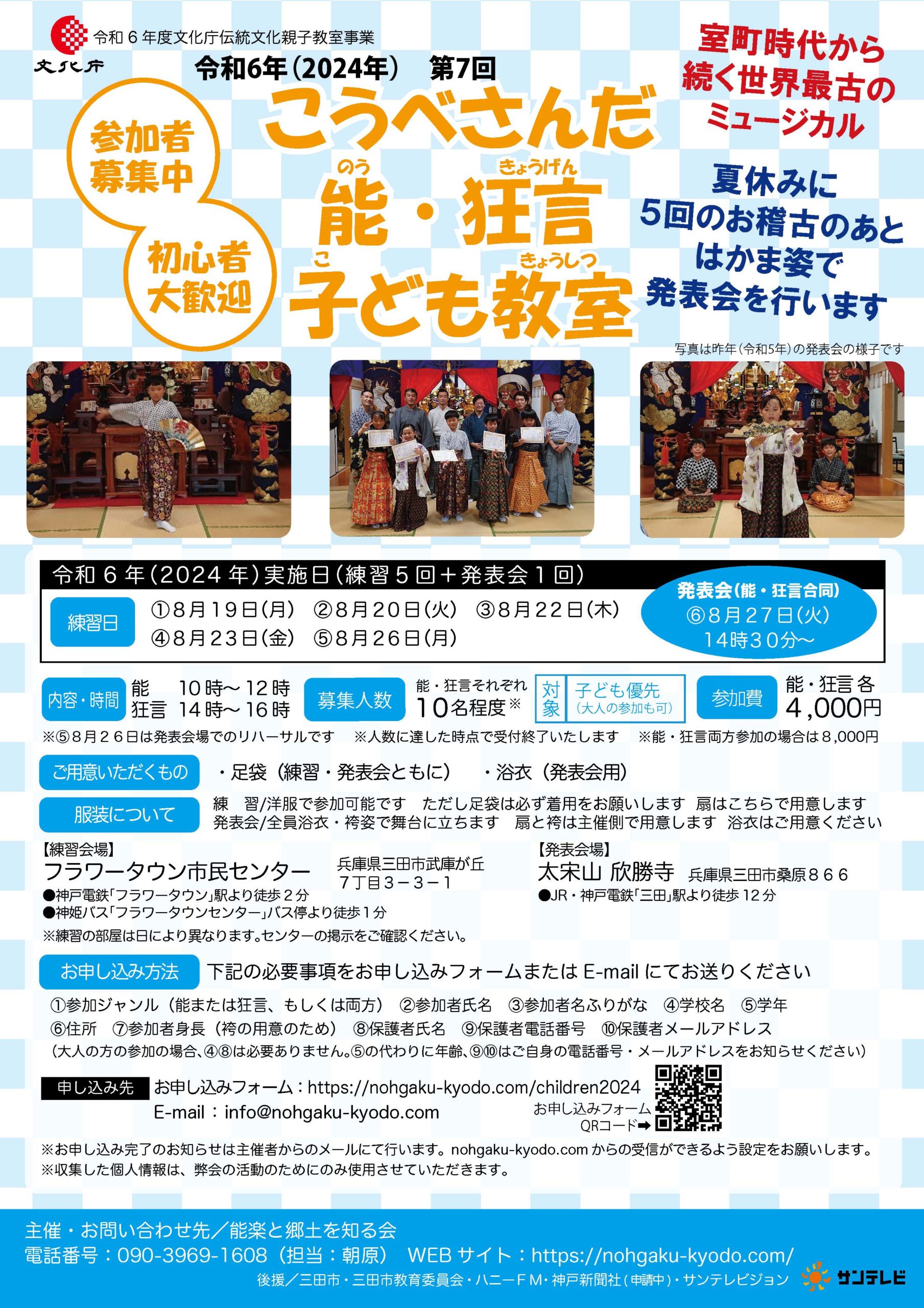能《殺生石》のことばを読みおえた雑感
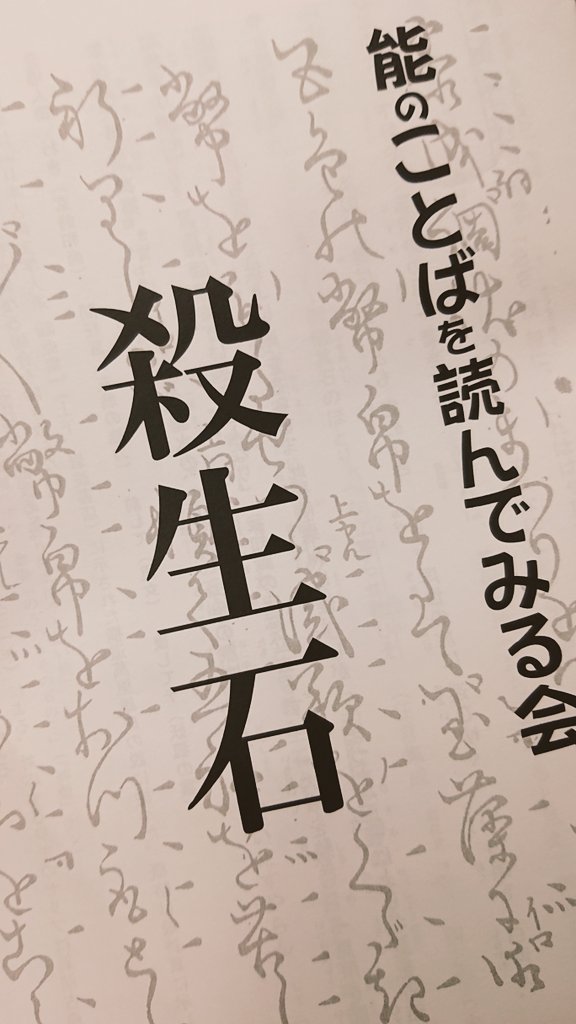
3ヶ月に1回開催しております「能のことばを読んでみる会」の第24回目、《殺生石》。令和元年12月14日土曜日に無事終了いたしました。ご参加いただいた皆様に御礼申し上げます。
《殺生石》という能は、那須野に現在も存在する巨石にまつわる伝説を能にしたてたものです。
玄翁という僧が、那須野を通りかかると巨石があり、その上空を飛ぶ鳥が突然落ちてくる。そこへどこからともなく女が現れ、その石の近くは危険だといい、その由来を語って聞かせる。
――昔、鳥羽院の時代、宮中に学芸優れた美女「玉藻前」がいたが、ある夜、秋風に燈火が消えた時、その玉藻の前が怪しげな光を放って宮中を照らした。それ以来、帝は病気となった。安倍康成に占いをさせると、玉藻前は化生の者(妖怪の類)であると分かった。その玉藻前が那須野まで逃げてきたが、死んだ後も執心が石となって、近づく人や動物を執り殺しているのだ…。
そこまで語った女は、実は自分こそが殺生石の石魂であると告白し、夜になったら真実の姿を見せる、といって石の中に姿を消す。
玄翁が仏事を行っていると、石が二つに割れて、野干の姿が現れる。野干の精は、天竺(インド)・唐土(中国)・日本に渡って、それぞれの王朝に危害をなしてきたというが、日本では安倍康成に占い顕され、この那須野で武士たちに討たれた様子を再現して見せる。討たれた後も、殺生石となって、人間や動物を執り殺していたが、こうして今、仏事を受けたことで悪心が去ったので、今後は悪事を行わないことを約束して姿を消すのだった。
玉藻前、源翁和尚と殺生石、安倍泰成、犬追物の起源…と多くの要素が混ざった話という印象が強いです。中でも、犬追物(犬を追って弓を射る弓術の作法)の起源説話は、「野干は犬に似たれば、犬にて稽古あるべしとて、百日犬をぞ射たりける、これ犬追物の始とかや」と突然入っている印象で、正直収まりが悪い印象もありますが、しかし、この能《殺生石》が作られた時に外せない重要な要素だったのでしょうね。
全体的には和歌や漢詩の引用がほとんどなく、そういう部分が世阿弥以来の作品とは違いますね。せいぜい上歌にある「梟 松桂の枝に鳴き連れ、狐 蘭菊の花に隠れ住む」が白楽天の『凶宅詩』の一部を少し形を変えて引用しているぐらいです(本来は「梟鳴松桂枝 狐藏蘭菊叢」)。これも漢詩のイメージを重ね合わせるというよりも、野干と同一視されていた「狐」が隠れる那須野…と導き出す程度の関連です。[1]やかん【野干】 中国文献や仏典に見える野獣。射干,射杆とも書く。狐に似て狐より小さく,群れをなして夜行する。よく木に登るので猿の一種とみなされることがある。司馬相如の《子虚賦》に,雲夢沢の密林の樹上に射干その他の鳥獣が住んでいることをうたっている。日本では狐の異名として用いられることが多い。(谷川道雄/執筆『世界大百科事典』平凡社より)
それよりも意味が難しいのは、ワキの名ノリの後や、石に対して引導を読み上げるあたりの禅宗用語です。それ以外は、クセもキリも、かなり素直に意味は取りやすい作品だと感じました。
《殺生石》の真価は作曲の妙、「画図の屏風」
後場は文章はまずまずだと思いますが、ワキの言葉から地謡に移るまでの部分が、節と詞を複雑に組み合わることで、三国をまたにかけた鬼神としての重みを描き、
その後は一転して、長い中ノリ地を続けることで、キツネが飛び跳ねているかのような描写に仕上げてあるあたり、《殺生石》は”作曲”の良い曲だなと感じました。
クセにある「打ち時雨吹く風に御殿の燈消えにけり、雲の上人立ち騒ぎ、松明疾くと進むれば、玉藻の前が身より光を放ちて、清涼殿を照らしければ」は、正直なところ、初めて知ったころは
「電気要らず、便利やん」などとひどい感想を持っておりましたが、照明がほとんどなかった当時、光というのは決して単に良いものではなくて、むしろ恐ろしい怪異だったのでしょうね。
その後にある「画図の屏風」は、『枕草子』21段にある「清涼殿の丑寅の隅の、北の隔てなる御障子は、荒海の絵、生きたる物どもの、恐ろしげなる、手長足長などをぞ描きたる」などのことだろうか、と想像を膨らませました。
『枕草子』に記された屏風は、つまりは能《大江山》の中入部分の地謡にある「荒海の障子」です。こうした古典同士のクロスオーバーに気付くと、読む側は本当に楽しいですね。
もちろん「画図の屏風」としか言っていないので、清涼殿にある絵が描かれた屏風ならば、荒海の障子に限る必要はないのですが。
とりとめもありませんが、「能のことばを読んでみる会《殺生石》」を終えた感想として、ここに記します。
脚注
| ^1 | やかん【野干】 中国文献や仏典に見える野獣。射干,射杆とも書く。狐に似て狐より小さく,群れをなして夜行する。よく木に登るので猿の一種とみなされることがある。司馬相如の《子虚賦》に,雲夢沢の密林の樹上に射干その他の鳥獣が住んでいることをうたっている。日本では狐の異名として用いられることが多い。(谷川道雄/執筆『世界大百科事典』平凡社より) |
|---|