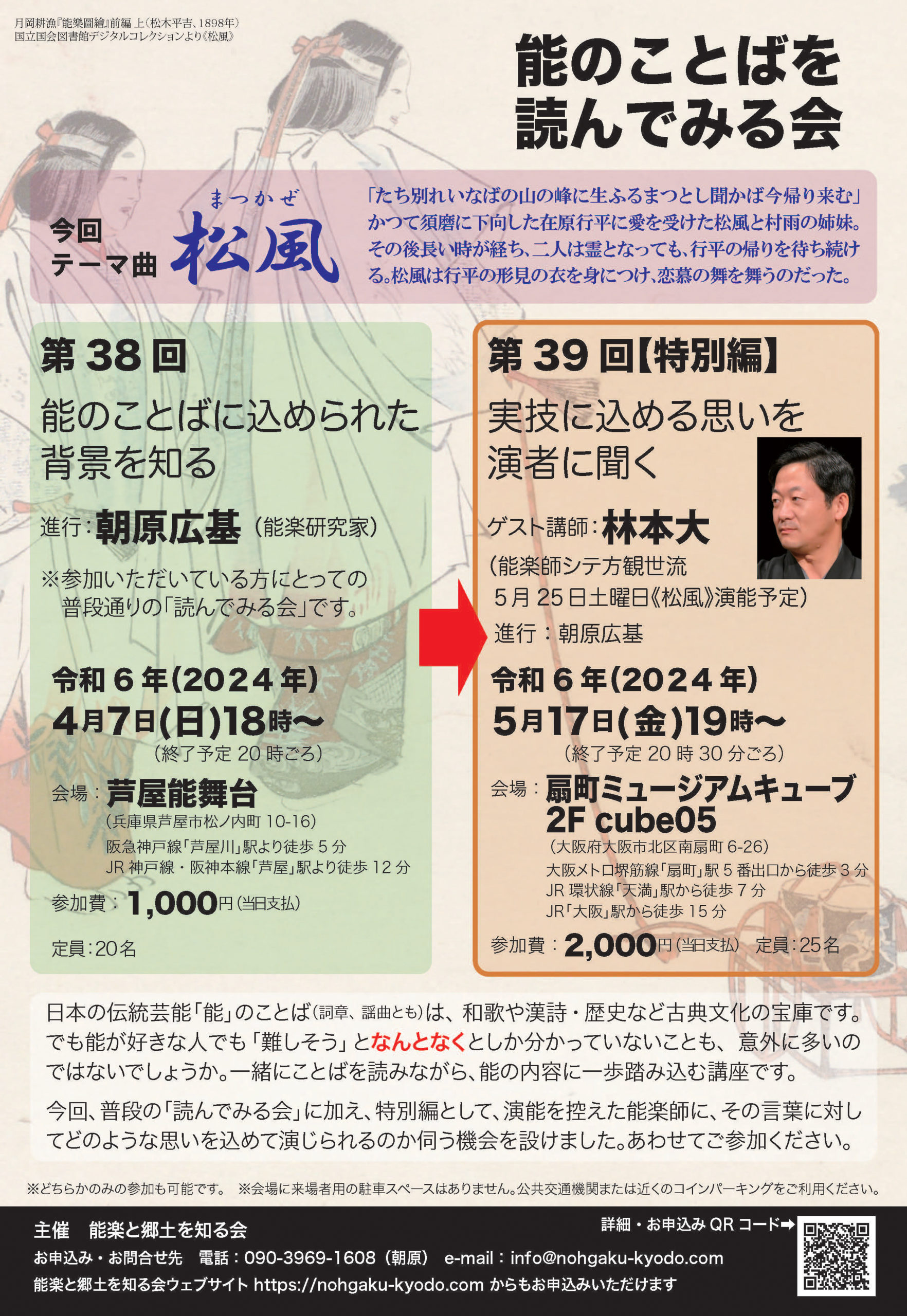三田藩主九鬼家の祈願所・三田天満神社

兵庫県三田市「天神」の地名の由来でもあり、丘の上から見下ろすように存在する三田天満神社。三田市内でも古い由緒を持つ神社の一つです。
古くは大歳神(農業神)を祀る社「三田神祠」だったそうですが、菅原道真の神輿が休んだという伝説があり、いつのころからか菅原道真の霊(天神)が祀られるようになり、主祭神となったようです。

元禄14年(1701年)に岡田溪志が刊行した摂津国の地誌『摂陽群談』には以下のように記されています。
現在の三田天満神社では、上記に記された赤松村秀による神像の奉納を、三田神祠の再建とみなしているようで、この時、現在まで続く三田天満神社の形がはっきりと成立した時期といえるかと感じています。
後、寛永10年(1633)三田藩主として九鬼家が入って以降は代々藩主の祈願所とされました。江戸後期成立の地誌『摂津名所図会』でも「三田神祠 三田村にあり。当城下産土神とす」と紹介されています。

享保19年(1734)に火災で社殿・社宝・記録などが焼失しますが、その後、三田藩七代藩主・九鬼隆由(たかより)が元文4年(1739)に寄進・再建したのが現在の本殿です。
平成30年(2018)3月にいたって、三田天満神社本殿は「入母屋造で華麗な彫刻が施されており、三田地方で18世紀中期の神社建築の指標として評価」され、兵庫県の登録文化財となっています。

古くから神仏習合が行われており、江戸時代までは別当寺院である「梅隆山松寿院」が現在の社務所の位置に存在し、祭祀を司ってきました。しかし、明治時代に入り、神仏分離令により仏教色は外され、明治6年(1873)に郷社、昭和3年(1928)に県社に列しています。

随神門は明治17年(1884)に再建されたもので、三田出身の文部官僚で男爵の、九鬼隆一による「遺徳燿萬春(徳を遺し萬春に燿く)」の扁額が掲げられています。

境内には、能舞台ではありませんが「舞殿」と呼ばれる立派な舞台があります。寛延2年(1749)の再建棟札あり。この舞殿を使用して、何らかの形で能楽の奉納を行うことができたらいいですね。
また『三田市史』には神宝として「翁面一面」と記されており、この神社も決して能楽と無縁ではありません。現在の社務所にも、奉納された能面が飾られています。
隣の天神公園は桜の名所で、春には大勢の人で賑わいます。