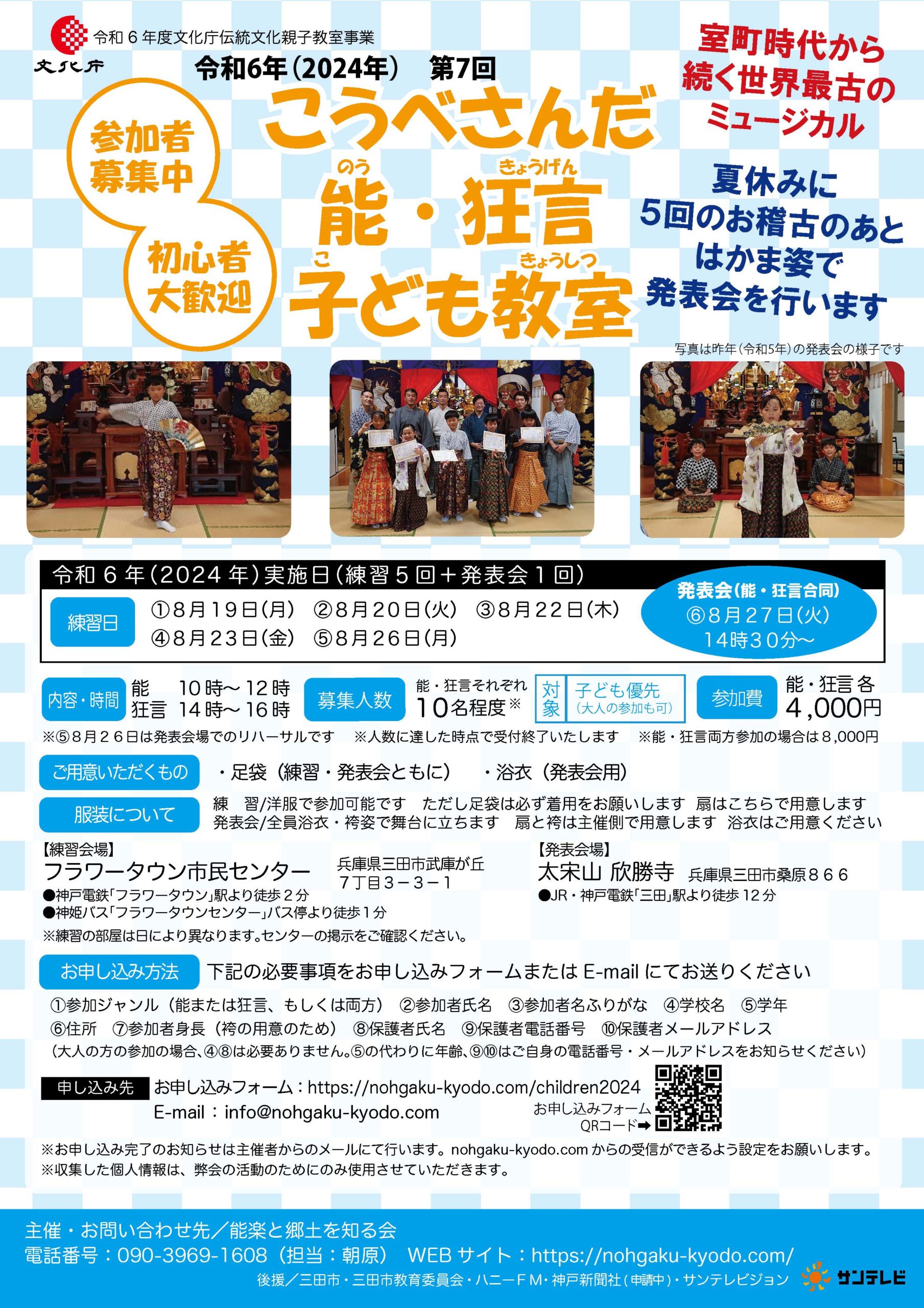【レポート】金春流・観世流・宝生流による「超流派・超能楽入門」

既に先月の話ですが、令和元年(2019年)7月24日(水)に、ホテル雅叙園東京で催された「能楽特別講座・シテ方四流若手能楽師によるトークセッション」に参加してきました。
これは、シテ方金春流能楽師の中村昌弘さんが年1回のペースで主催されている四流講座の5回目です。まずここでは、昼の部として開催された「超流派・超能楽入門」を一部だけですがレポートを記します。[1]なおこの記事の内容について、あくまで筆者が当日に取ったメモおよび記憶に基づいたものです。もちろん可能な限り再現したつもりですが、それぞれの話者が実際に話されたことや認識と異なる可能性があります。その場合の責任は私にございます。あらかじめ、明記させていただきます。
講師は主催の中村昌弘さん、そして観世流・武田宗典さん、宝生流・高橋憲正さんの3人。
今までは国立能楽堂の講義室で開催されてきたのですが、今回は豪華な雅叙園の会場です。中村さんも少し緊張気味でした。
流儀による「声の出し方」の違いと共通点
まずは《四海波》と呼ばれる《高砂》の一節を、スライドで各流派の謡本を表示しながら実際に謡比べから。それぞれの声の出し方や、その際の心がけなど、それぞれの経験談を引き出します。
このような流れをうけて、再び武田宗典さんが
と謡の発音一つをとっても、以上のような深い実技者ならではの会話が繰り広げられます。
タイトルにある「超入門」が吹き飛ぶ内容ですが、この会話自体が大変魅力的なもので、単に基礎知識的な内容よりも刺激的で、その面白さを感じる心が「超入門」になりえると強く感じました。

そのあと、謡本の表記の差、節表記の違い、音の高さ、のどのケア、息の吸い方……と謡だけでも、非常に突っ込んだ話になりました。
さらに話題は謡だけにとどまらず、面の話・装束の付け方・扇・カマエ・型などの話にも展開し、話題が多すぎて全てを、文字に起こすことは私の手には余りますし、私の勘違いもあるかと思うので、あまり詳細には触れません。
ただ、それぞれ流儀も個性も違う3人だけに、詳細は異なることが多い一方で、時々不思議に一致することもあり。その一致する点が、「能とは何なのか」という能全体の特性論にもつながるのではないか、と私は想像しています。
超流儀の装束着付も
個人的にツボだったのが、シテ方金春流である中村さんに、異なる流派である武田宗典さんや高橋憲正さんが、金春流の女性能楽師さんたちの手伝いを受けて、装束を実際に着ける場面。私、能の楽屋で装束付をする姿も数多く見てきましたが、流儀が違う人に着付けをするのは本当に珍しいのです。

これは、腰巻の付け方が観世流と宝生流で異なる[2]なお、金春流は観世流と同じとのこと。という実践だったのですが、宗典さんが「腰巻紐がないんですね…」と地味にショックを受けていた図がハイライト。
観世流では腰巻の際には専用の腰巻紐を使うのですが、金春流では唐織紐を使用するようです。実践としてはどちらでもできるようでしたが、こんなところにも流儀の習慣の差があるのだなと、マニア心を刺激されまくりの時間でした。